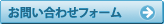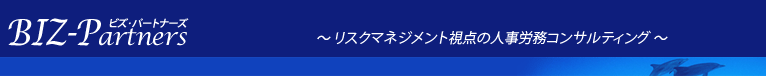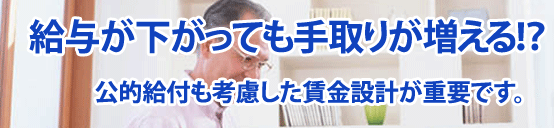
知らないうちに余計なコストをかけていませんか?
- 再雇用後の賃金は定年時の75%より60%のほうが本人手取額が多い?
- 65歳までの定年延長よりも、65歳までは1年更新の嘱託社員にしたほうが会社コストは安い?
- 再雇用後の賃金を60歳時の賃金の75%未満に設定すると雇用保険から給付がもらえる?
- 再雇用制度ならば社会保険の特例で60歳到達後すぐに再雇用後の賃金額を反映した保険料になる?
- 実は59歳の時の賞与は出来れば支払わないほうがいい?
【改正雇用安定法の施行】
御社では従業員の方が60歳定年を無事迎えられた場合、その後の継続雇用制度についてはどうされているでしょうか?ご存知のように平成18年4月1日より定年に関する法律(高齢者雇用安定法:以下「法」)が改正になり、定年を迎えられた従業員の方が定年後もその会社で働き続けることを希望した場合にはその受け皿として会社は以下の3つの制度のうち何らかの制度を導入し65歳までの雇用を確保する準備をしなければならなくなりました。
(1)定年の廃止
この制度を導入するということはつまり、従業員の方が自ら辞めると言い出さない限り、会社からは年齢を理由に辞めてくれとは言えなくなるということです。法改正後、実際にこの制度を導入している会社は殆どありません。
(2)定年年齢の延長
この制度はこれまで60歳だった定年を65歳に延長するということです。(平成25年3月31日までは老齢厚生年金の受給開始年齢の引き上げに応じて62歳から64歳まで順次引き上げていくことになっています。)この制度を導入した場合、60歳までの賃金を下げることは簡単には出来ません。また、会社に退職金制度がある場合もコストは増大することになります。
(3)継続雇用制度の導入 → 再雇用制度
この制度は60歳で一旦、定年退職として雇用契約を終了させた後、改めて雇用契約を締結し、再雇用するということです。新たな労働条件のもとに雇用契約を締結することができ、基本的には労働時間を少なくする、もしくは賃金を下げるということが自由にできます(ただしこの場合でも最低賃金法の適用は受けます)。
会社側が提示した労働条件に納得できず、結果として60歳定年でそのまま従業員が退職したとしても、法違反とはなりません。ただし適切な制度運用を行わないと、労働基準法をはじめとした法律に抵触する可能性もあるので、注意が必要です(例えば年次有給休暇を60歳定年による退職を理由として、すべてリセットするといった運用を行うと、労働基準法違反となります)。
それでも(1)、(2)の制度に比べて、会社としての人件費コストの増大を防ぐことができ、制度としても比較的導入しやすい制度でもあるので、法改正施行後、この制度を導入している企業の割合が一番高くなっています(約9割の企業が導入:厚生労働省データ)。
※(3)の継続雇用制度の導入については原則として希望者全員の再雇用を前提としていますが、労使協定を結んでいることを条件に、会社側が再雇用する為の基準を設けることが出来ます。
【高齢者雇用・最適賃金に関するお問い合わせ】
お電話か、お問い合わせフォームにて、お気軽にお問い合わせください。
法人コンサルティング部 吉永・吉田 TEL:03-5682-7737 (平日9時〜17時)