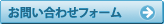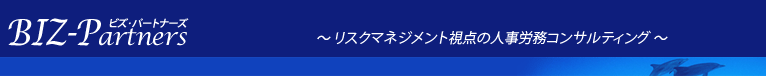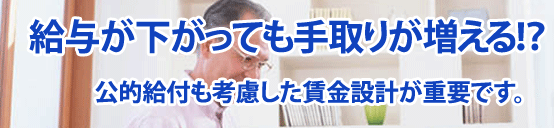
再雇用賃金設計の注意点とポイント
①再雇用後の契約形態によっては年金は全額支給
再雇用された後に社会保険に加入すれば、その賃金に応じて年金額が支給停止となります。しかし、パートタイマーやアルバイトなどの雇用契約で働く場合は社会保険に加入しなくても良い場合があります。平成19年9月時点では勤務時間または勤務日数が一般の社員に比べて4分の3未満の場合がそれに該当します。高齢者を再雇用する場合は定年前よりも労働時間や日数が短縮されることも多いでしょう。従って所定労働時間を通常の4分の3未満になる労働条件の方は社会保険に加入しなくてもいいので、年金を最大限活用した賃金設計が可能となります。
②同日得喪とは?
「同日得喪」とは一言で言うと「同じ日に社会保険の資格を喪失し、再取得すること」です。この制度は60歳代前半で老齢厚生年金をもらえる人が、定年で退職し再雇用された場合に適用される特例です。この制度を適用するためには会社に定年による退職が明らかに出来る書類があることが必要です(就業規則、退職辞令など)。
この制度を適用すると、再雇用後の減額した賃金による社会保険料がすぐに反映されますから、年金の支給もタイムリーに行われることになります。しかし、この制度を適用しないとどういうことになるかというと、せっかく最適な賃金設計のシミュレーションをしても実際にシミュレーション通りの額になるのが定年退職後約5ヵ月後になってしまいます。それではせっかくのシミュレーションも用を成さず、会社のコストも削減効果が出るのが遅くなってしまいますから、この「同日得喪」はタイミングをずらさないことが肝心です。
③賞与が与える影響とは?
在職老齢年金の支給停止額を決める際、「総報酬月額相当額」というものが影響してきます。「総報酬月額相当額」とは月々の給与額=標準報酬月額にその月以前1年間の賞与の額を12で割った額を足したものです。(賞与は標準賞与額で計算します)つまり、59歳から60歳になるまでの間に支払われた賞与の額が、在職老齢年金の額を決めるときに影響してくるのです。仮に59歳から60歳の間に支払われた賞与が以下の通りだとすると・・・
59歳の夏の賞与 (7月支給) ※ 60歳以降は賞与が支給されないという前提です。
59歳の冬の賞与 (12月支給)
この場合、60歳到達が仮に3月だとすると、4月〜6月は7月の賞与と12月の賞与が総報酬月額相当額に入ってきます。 そして7月〜11月は12月の賞与が総報酬月額相当額に入ってきます。そして12月以降は59歳の夏と冬両方の賞与が反映されないで計算されます。つまり60歳到達以降8ヶ月間は3回、在職老齢年金の額が変わるということになるのです。 この変動によって、本人の手取額は当然変わって来ますから、シミュレーションも少々、厄介なことになりますね。出来れば、 59歳の賞与については、支払わないか、あるいは少ない額で一定の額にしておくことをお勧めします。ただ、本人にとってはモチベーションを下げることにもなりかねませんので、下げた分を退職金に反映させるなどの代替措置が必要です。
以上のポイント以外にも、賃金設計の際には注意すべき点があります。この設計は確かに、会社側にとっては賃金を減らすことが出来て、社会保険料も削減できますから、コスト削減という意味では有効な方法です。ただし、賃金を下げられるほうの従業員にとっては慎重な対応が必要となります。賃金の下げ方によっては手取額の減少が抑えられることばかりではなく、再雇用後の本人にどういう業務を望むのか、そしてどういうレベルの生産性を設定するのかによって一律の賃金体系を敷くのではなく、できるだけその勤務別の賃金体系を設定することが望ましいでしょう。先に述べた法改正の内容などを踏まえた上で定年を迎える個人個人の再雇用について考えるのではなく、会社として再雇用に対する考え方をふまえた再雇用制度を設計、運用する必要があります。当社では会社ごとの実態に合わせた御社独自の再雇用制度設計お手伝いいたします。
【高齢者雇用・最適賃金に関するお問い合わせ】
お電話か、お問い合わせフォームにて、お気軽にお問い合わせください。
法人コンサルティング部 吉永・吉田 TEL:03-5682-7737 (平日9時〜17時)